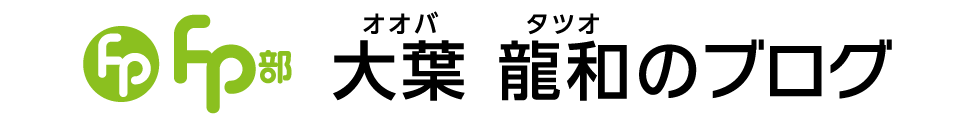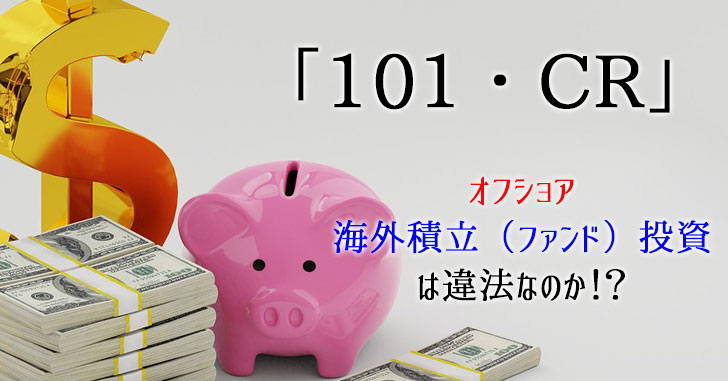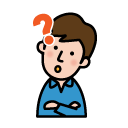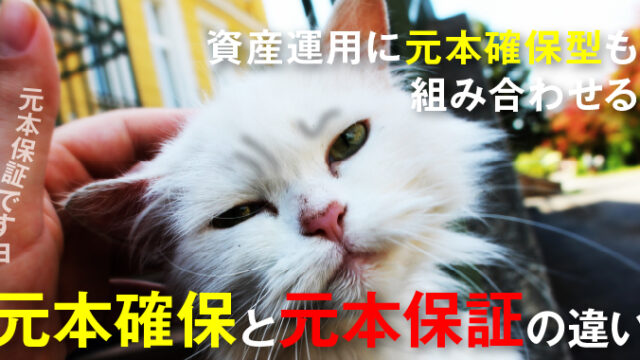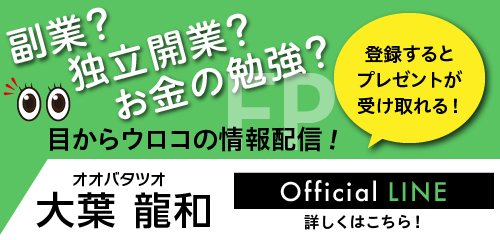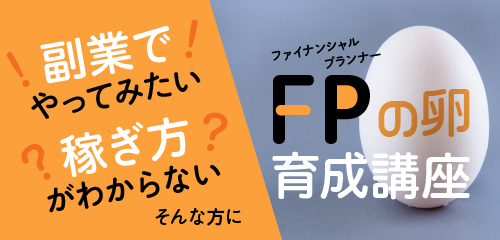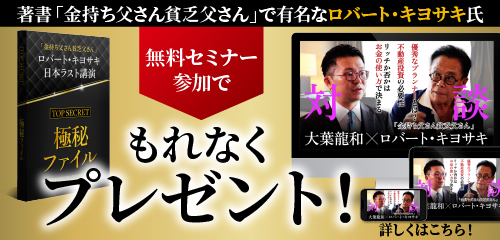オフショア海外積立投資って、
違法性は
あるのでしょうか???
まわりの友人から
勧誘されているのですが、
違法性があるなら
やりたくないですし…(´-ω-`)
本当のところを
教えてくれませんか?
上記のような質問、
独立系FPとして現場に居ると、
クライアントさんから質問される
ケースがあるんですよね。
で、以前の記事(下記参照)では、
フワっと、ぼやっと、
- オフショア保険
- オフショア投資
- 海外積立保険
に関しての法律の話を書きました。
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
上記では商品を絞らずに法律のことを
ふわっと触れた感じですが、
今回は、
「ファンド購入型」の
「オフショア海外積立投資」
と敢えて限定した書き方で
書いていきます( ..)φメモメモ
というのも、
このファンド購入型を
紹介しているFPがマーケットに多いので、
質問が一番多いのも
このファンド購入型の商品ですので。
あ、ちなみに、
立場をハッキリさせておきますが、
このブログの著者である私は、
ファンド購入型の商品は
オススメしていません!(゚д゚)
ですので、
「最後にこちらを~~クリック!(^^♪」
でファンド購入型に誘導するような
ことはしませんので、
ご安心ください(笑)
では、書いていきます
( ..)φメモメモ
ファンド購入型のオフショア海外積立投資のイメージ
まずは、イメージの話からいきます。
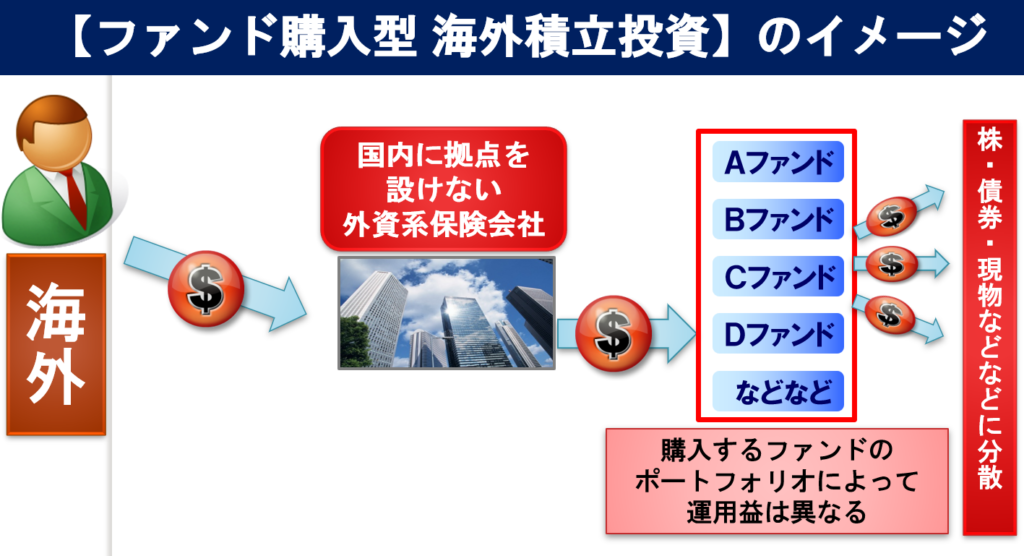
上図にあるように、
契約者が出したお金は
海外にある保険会社を経由して、
その資金の
100%が「ファンドや債券などの購入」
に充てられます。
どのくらい資金が増えるのか?
(減るのか?(笑))は、
購入するファンド次第となるので、
元本が棄損する可能性も当然にあります。
101型:ファンド購入型のオフショア海外積立投資
さらに細かく見ていきます。
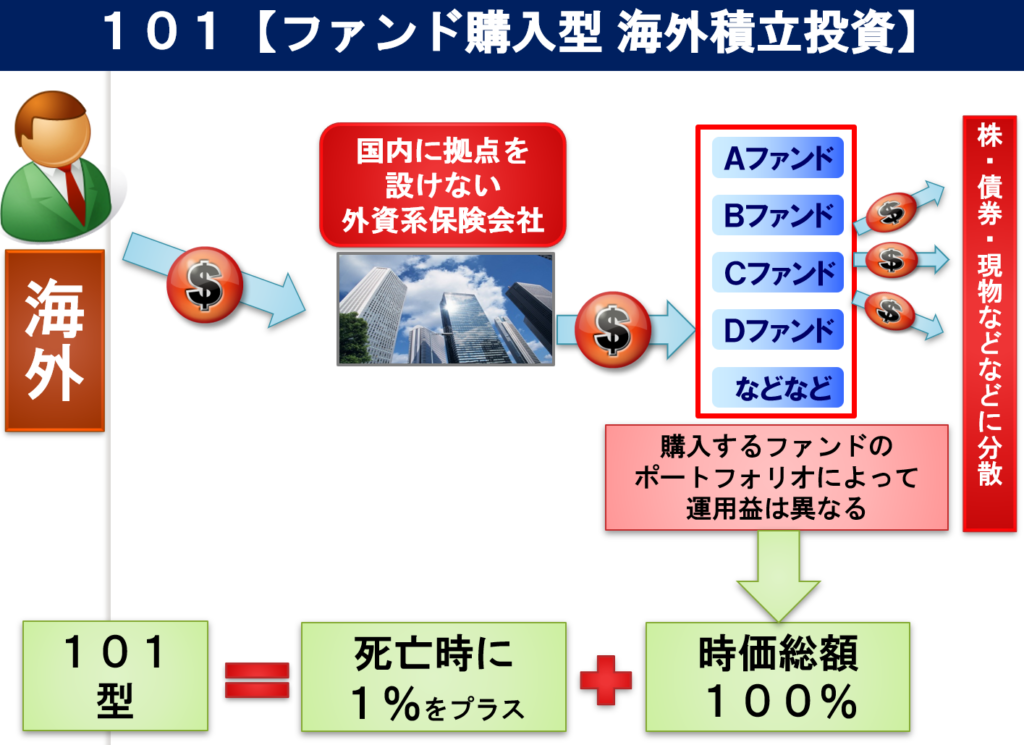
繰り返しになりますが、
契約者が出したお金は
海外にある保険会社を経由して、
その資金の【100%】が
ファンドや債券などの購入に充てられます。
例えば、これが
1000万円のボリュームがあるとします。
で、もし契約者が死亡した時は、
1000万円(100%部分)
のほかに、
別に10万円(別に1%)が
プラスされて、
1010万円が受益者
(遺族など)に
支払われるという
ルールになっています。
はい、つまり、
100%+1%
=【101%】
となるわけです。
これが、101型と呼ばれる
オフショア海外積立投資なのですが、
日本の法律に当てはめた場合の
分類が難しい商品となっています。
100%部分のファンドだけなら?!:金商法?!
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
100%部分に該当する
ファンドだけならば
金融商品取引法による管轄に
なるだろうとされています。
で、上記の記事で書きましたが、
金融商品取引法による見解だと、
クライアントサイドは
➡買っても良いけど
業者サイドは
➡売ってはいけない
というルールになります。
また、紹介者であるFPに対しては、
利殖勧誘というペナルティが
発生する可能性が残されます(゚д゚)
1%の死亡保障が付くと?!:保険業法?!
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
1%の死亡保障が付くということは、
保険商品として機能があるわけで、
保険業法の解釈にもなり得るのか?!で、
またまた上記の記事で書きましたが、
保険業法による見解だと、
101型は法的見解が不明
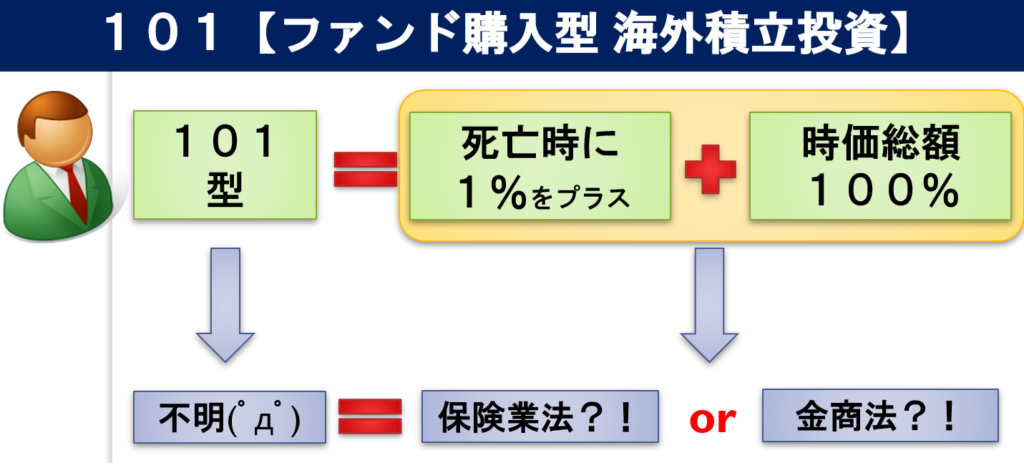
現在のところ、
(分類のしようが無い
というのが正確な表現
にはなるのですが。)
ただ、
分類のしようが無いからと言って、
FPとして好き勝手
販売していいのか???
という議題に関しては、
僕個人の見解としては
「NO」だと思います
( ..)φメモメモ
今後、この101型の商品が
金融商品として認定され、
金商法の適用を受けた場合は、
紹介していたFPは
金融商品をノーライセンスで
販売していたという問題
にさらされる可能性
もありますし(゚д゚)
また保険商品として認定されて、
保険業法の適用を受けた場合は、
次は、契約者である
クライアントさんサイドが
ペナルティを負う
可能性が出てきます(゚д゚)
結果、無責任な販売はNGと
言わざるを得ません…
実際は無責任な販売をしている
FPが多いんですけどもね
(´・ω・`)う~ん
次にCR型:ファンド購入型のオフショア海外積立投資
次は、101ではなく
CRと呼ばれるファンド購入型の
オフショア海外積立投資の話です。
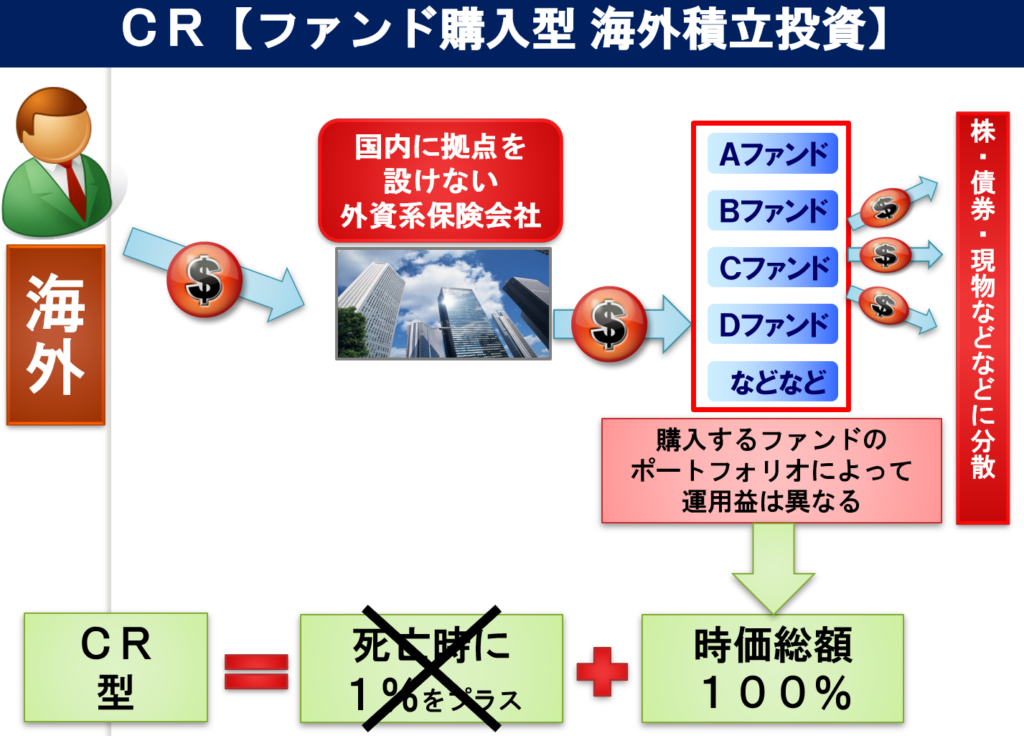
上図を見てもらうと、
大まかな構造に
そもそも違いはありません。
(ここでは、CRは満期時に
強制的に資金が償還される~等の
細かいルールは一旦除きます。)
違いがあるとするならば、
死亡時に
【1%の死亡保障が付かない】
という点です。
1%の死亡保障が付かないということは、
法的見解の分類が行いやすくなります。
CR:ファンドなどの100%の時価総額
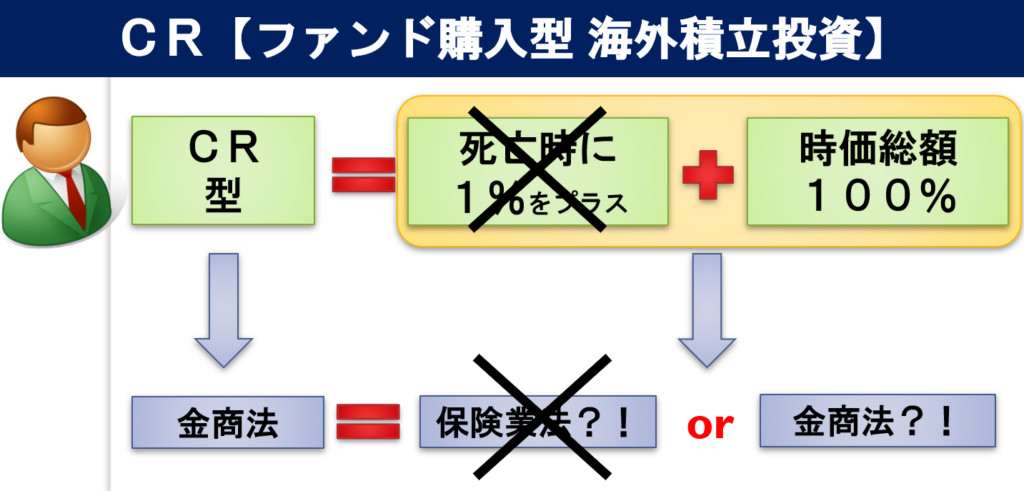
上図にあるように、
シンプルにファンドなどの
100%時価総額部分だけの
話になりますので、
オフショア保険・オフショア投資・海外積立保険は法律違反か否か?!
またまた出てきましたが、
上記の記事で書いたように、
金融商品取引法による見解だと、
クライアントサイドは
➡買っても良いけど、
業者サイドは
➡売ってはいけない
というルールになります。
また、紹介者であるFPに対しては、
利殖勧誘というペナルティが
発生する可能性が残されます(゚д゚)
CR:クライアントは明確にOK
金融商品取引法による見解だと、
クライアントサイドは
➡買っても良いけど、
業者サイドは
➡売ってはいけない
というルールになります。
ということは、
クライアントサイドは
【海外積立投資はOK】
と法的に言えることになります。
ですが、逆にFPサイドは、、、
CR:紹介者であるFPは利殖勧誘の可能性
紹介であるFPは
利殖勧誘とペナルティを
課せられる可能性があります。
CRと101の違い
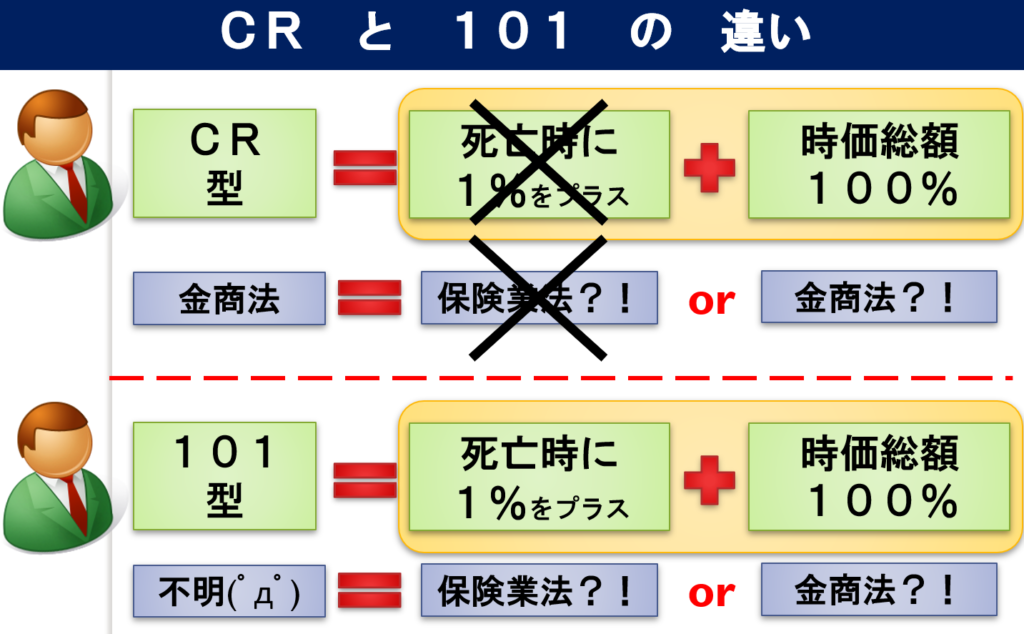
もう一度おさらいすると、
上図のようになります。
で、ここで、
解釈されるのか???
と質問されることもあるのですが、
過去、日本において
裁判で問題になったのが
このCRの商品です(゚д゚)
つまり、
一度問題視されている例があります
( ..)φメモメモ
また機会があればこの辺りも
細かく記事にしたいと思いますが、
とにかく、法的に問題になった
実例があるということです、
はい。
逆に、
101は未だに「不明」という
立ち位置のままです(゚д゚)
著者である僕がファンド購入型を扱わない理由
ちなみに、僕が
ファンド購入型の
オフショア海外積立投資を
扱わない理由は、
そもそものお話として、
ファンド購入型は
リスクが大きい&内在する
(表向きは説明されていない)
手数料が高い、という
デメリットが大きい
と思っているからです
( ..)φメモメモ
さらに、CRの場合は、
金融商品をノーライセンスで
販売・紹介することになるという
「違法性」の問題も浮上しますので、
なおさらNGです(゚д゚)
まとめ
オフショア海外積立投資って、
違法性は
あるのでしょうか???
まわりの友人から
勧誘されているのですが、
違法性があるなら
やりたくないですし…(´-ω-`)
本当のところを
教えてくれませんか?
CRの場合は、
紹介している
FPに違法性が出てきますし、
101の場合は
法的見解は不明、というか、
分類が出来ていないというのが
正確な回答になるかと思います
( ..)φメモメモ
契約者である
クライアントサイドから見た法的見解と、
FPという立場から見た法的見解
は違いますので、
この辺りもしっかりと
理解する必要はあります(゚д゚)!
ということで、今回はここまで~!
高単価FPの育成
副業FP卵の育成
⇒ 【無料動画&無料セミナー】