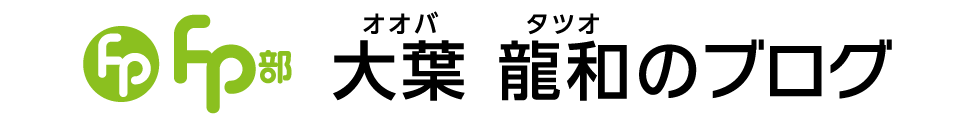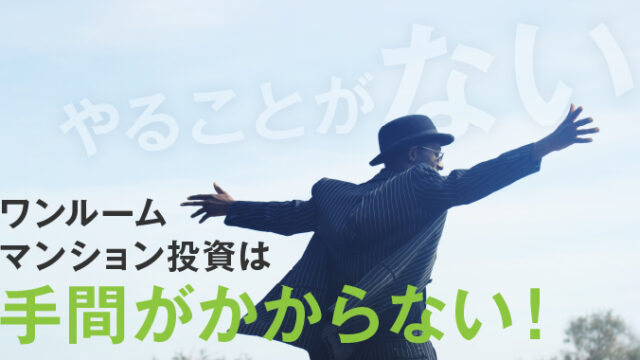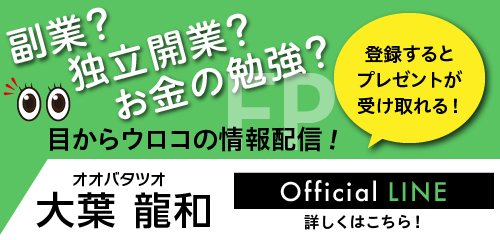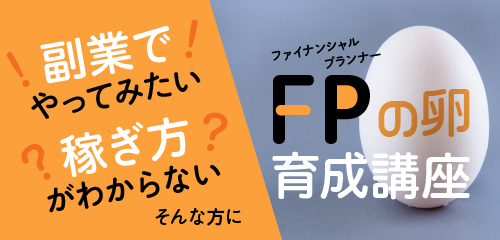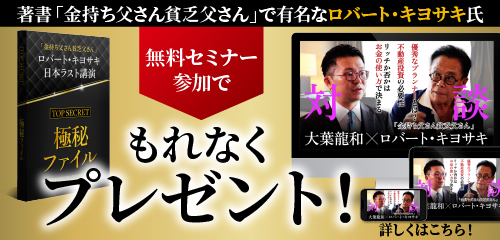不動産投資を行う際に、
「法定耐用年数
(ほうていたいようねんすう)」
は気にしている方は多いかと思います。
減価償却で節税のスピードにも
影響する話ですし。
ただ、
【残法定耐用年数
(ざんほうていたいようねんすう)】
の【残】を気にしている方が
意外に少ないように思います( ;∀;)
ということで、今回は
法定耐用年数と残法定耐用年数のテーマで
記事を書きます( ..)φメモメモ
大事な大事な話なので、
FPとして不動産投資の
アドバイスをしようと思う方は、
是非とも理解してくださいね!
法定耐用年数と減価償却
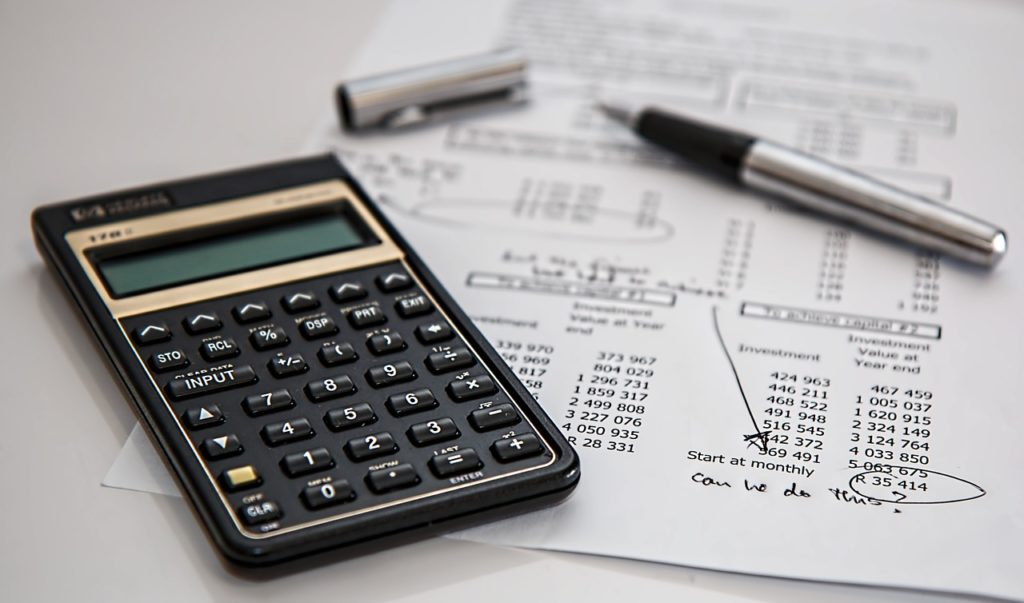 まずはおさらいですが、
まずはおさらいですが、
で、この法律上の
使用可能な年数に応じて
順次経費として計上する
会計処理のことを減価償却と言います。
はい、ワケが分からないと思った方は、
以下の記事に詳細を書きましたので
見てみてください!(笑)
不動産投資の法定耐用年数は?
不動産の場合、
- 木造
- S造(鉄骨)
- RC造(鉄筋コンクリート)
で法定耐用年数がそれぞれ
設定されています。
木造
22年
S造
19~34年(鉄骨の骨厚による)
RC造
47年
と決まっています。
ちなみに、
実際に上記の19年~47年で
不動産が倒壊したり
するわけではありません(笑)
実際の耐用年数の話を
しているわけではなく、
法律上定められた法定耐用年数の
話をしています。
上記の数値は
不動産投資を実践している方は
よく理解している数値かと思います。
上記のそれぞれの数値を基本として、
【残】法定耐用年数の話が出てきます。
残法定耐用年数とは?【残】が大事!
例えば、10年経過した
中古不動産で考えてみます。
元々の法定耐用年数としては、
木造は22年
RCは47年
です。で、
今10年経過しているわけですから、
残っている年数は、、、
木造:22年-10年
=12年(残法定耐用年数)
RC:47年-10年
=37年(残法定耐用年数)
となります。
で、この【残】法定耐用年数が、
原則として、
「金融機関が融資するMAXの期間」
となります。
「法律上定められた使用できる年数」
=「法定耐用年数」
にのっとって、
金融機関は融資期間を設定するわけですね。
中古になると、必然的に
法律上定められた【残りの】
使用できる年数
=【残】法定耐用年数
にのっとって、
金融機関は融資の期間を
設定するわけです。
で、なぜ、残法定耐用年数が
大事かというと・・・
不動産投資の出口としての売り抜け(売却)が難しくなる
不動産は
次の買い手が見つかって始めて、
売却が成立します。
で、次の買い手が
金融機関で融資を組んで
不動産を購入する際の融資期間が
【残法定耐用年数】に縛られるわけです。
次の買い手にとっては、、、
融資期間が短くなる
↓
返済期間が短くなるため、
毎月の返済金額が
どうしても大きくなる
↓
毎月のキャッシュフローが
大きく崩れる
↓
融資を組んでまで
購入しようとしなくなる
↓
売却が成立しない・・・
という流れも想定できます。
融資条件を好条件なモノに組み直すのが難しくなる
経過年数と共に、
残法定耐用年数もどんどんと
減少していきます。
不動産投資の場合、
金利が安くなったりするタイミングで
融資の借り換えをして、
もっと有利な条件の金融機関から
借り直すことがあったりします。
ただ、
【残法定耐用年】内でしか、
原則としては借り換えができません
ので、
中古不動産を保有している場合は
注意が必要です。
新築のRC造(鉄筋コンクリート)は47年、最強です!
残法定耐用年数の発想で考えると、
RC造の47年という数値が
MAXのベストな数値と言えます。
で、ここにきて、
35年ローンではなくて、
【45年ローン】という融資が
始まっていたりします。
ただ、この
45年ローンが組める
=45年の法定耐用年数が残っている
必要があるわけで、
RC造の新築不動産か、
超築浅不動産しか
この45年ローンは組めません。
もし、45年ローンが組める
新築の好条件
ワンルームマンションがあるなら、
絶対買い!と言えるわけです
( ..)φメモメモ
※もちろん立地や
諸々の注意点はありますが。
まとめ
不動産投資の
アドバイスの中には当然、
出口戦略の話も出てきます。
その際、
✅融資を好条件の融資に
借り換えたらいい…
と軽々しく
アドバイスをしている方もいますが、
実際のところは、
基本原則としてのルールとしては、
【残法定耐用年数】を考えないと
いけなかったりします。
(金融機関の中には、
この【残法定耐用年数】は
無視した形の融資をする
ケースもありますが。)
ということで、
FPとして不動産投資の出口戦略の
アドバイスをする際には、
残法定耐用年数に関しては
当然に理解しておくべき
ポイントとなります。
ということで、今回はここまで~!
高単価FPの育成
副業FP卵の育成
⇒ 【無料動画&無料セミナー】